【隔週刊】「雪と梅の花のコントラスト」「それでも歌えますか?」「政府は国連から勧告受ける」「大人が守るのは子どもたち」他 2025/4/5

熱血お母さん100% 市議会で奮闘!
あなたは、もっと たいせつ にされるはずの人なんだ
■雪と梅の花のコントラスト
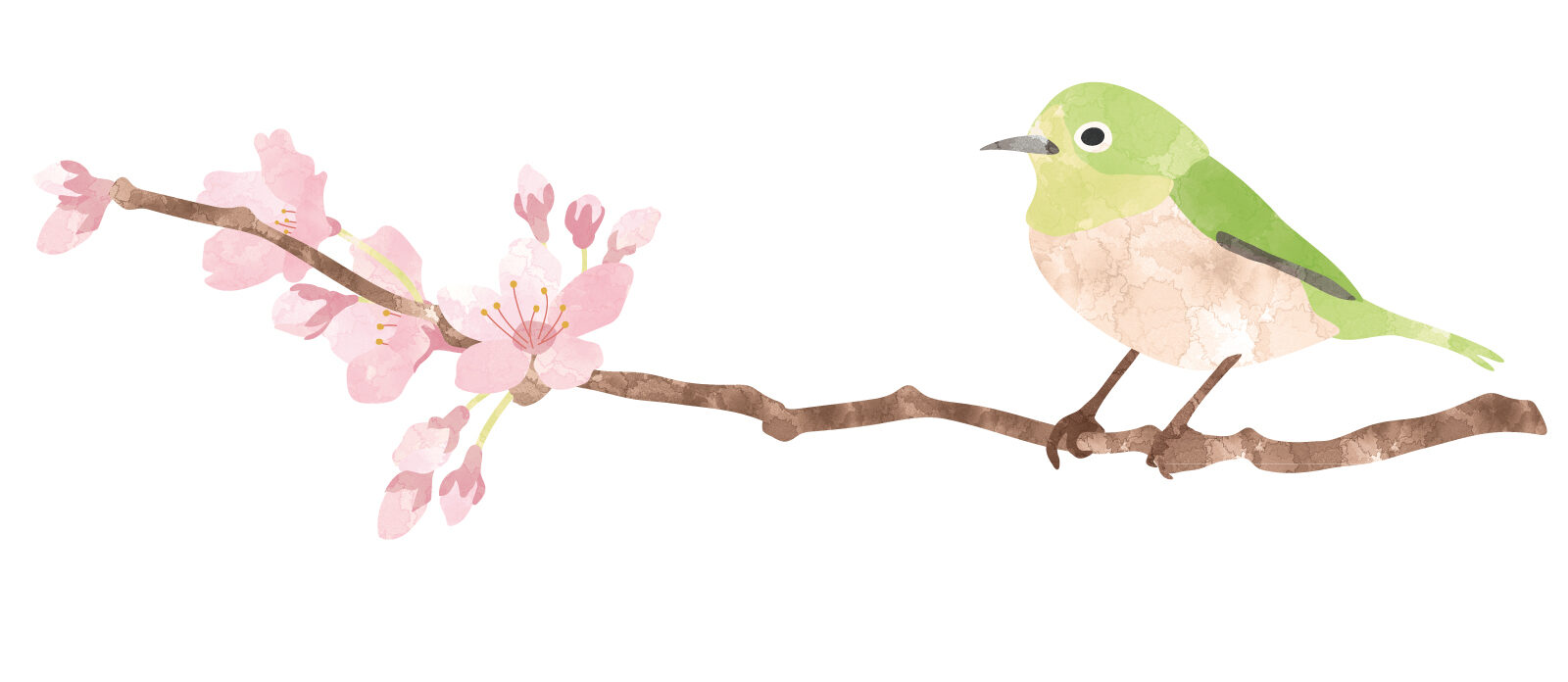
3月4月は卒入学式の時期ですね。
私は毎回、近くの小・中学校へ来賓として参加させて頂いております。流れとしては、教育委員会から市議会議員へ来賓の案内書類が届き出席させていただきます。
2025年3月19日、三鷹市立の全中学校の卒業式でした(小学校は25日)。朝から雪がたくさん降っており、春先の雪を喜ぶ人と、服装や交通移動に困る人、どちらの方もいたことと思います。
子どもたちや保護者にとっても、「いつもより早く出発しなきゃ!」「車で送って!」「タクシーか…」などの対応に迫られる等、印象深い日になったのではないでしょうか。
私も子どもたちを着替えさせて朝ごはん食べさせて、「抱っこして~」と抱っこタイムがあり、ドタバタでピンクのスーツ上下に黒い長靴履いて早歩きで向かいました。学校に到着して来賓待合室に案内され、窓から外をふと見た時に「雪の白色と梅の赤の色合いが美しいな」と、目を奪われてしまいました。
■それでも歌えますか?

会場である体育館への入場の順番は、在校生と保護者と教員が先に着席。次に来賓が入場、最後に卒業生がクラス順に入場。
全員が着席すると、これから卒業式を始めるという「開会の辞」が行われ、「一同起立」で全員立ち、「国歌斉唱」という流れでいきなりやってきます。
全員が立っている中で、私1人、着席をしました。「着席」と言われてもいないのに。
なぜならば、私は、「君が代」が歌えないからです。歌詞やメロディーを知らないわけじゃありません。もちろん小学校の頃から、幾度も歌わされてきたから、完全に染みついている。いつだって歌える状態になっています。
むしろ率先して大きな声で歌ってきたタイプで、「みんなが歌う時の流れで1人歌わない人って、一体なんなんだ?」とさえ思っていました。
しかし今、私には歌えない理由があるのです。
それは、子どもたちを守るためだからなんです。
■政府は国連から勧告受ける
まずは「日の丸」「君が代」を受け入れることができない子どもの「思想・良心の自由」を守ることが重要です。
そしてその子どもたちを守る教員も守らなくてはなりません。
2019年、日本政府は国連機関から叱られました。ILO(国際労働機関)とユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が日本政府に対して、「国歌斉唱強制の是正を求める勧告」を行いました。日本政府は,「日本の人権保障は、国際基準に達していない」と、国連機関から指摘されたのです。
そりゃそうなんです!

さかのぼりまして、日本の流れとしては、1999年に制定された「国旗及び国歌に関する法律」により、学校行事での国旗掲揚と国歌斉唱が推奨されました。
更に、2003年10月23日、東京都教育委員会は、教職員に対し、卒業式、入学式等の式典において「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした通達をしました。
「あたりまえじゃん!」と思う方もいるかもしれませんが、そもそも、国旗・国歌にたいする態度を教育現場に強制する国というのはあまりない。なぜなら、「国を敬うこと」の強制は、民主主義とは相容れません。自由に意見が言えること、特に政治問題や公共の問題について、誰もが自由に批判できることが、民主主義の原動力となるからです。
国旗や国歌は強制すべきもの・強制されるもの?
なのでしょうか。そもそも、国歌を斉唱している人だけが、国を敬っているのでしょうか。歌わずに黙って敬意を表してもいいはずです。大声を張り上げて絶唱する人だけが、国歌を敬っていることにはなりません。このことについて、サッカー選手のメッシは、国歌を歌わないことを批判されたことに対し、「僕は国歌を歌う必要はないと思っている。愛国心を感じているけど、歌わなくても何も変わらないだろう」と語っています。敬意を表すかどうかも、敬意の表し方も、人それぞれでいいはずです。
「国旗・国歌を敬うのは大切なことだ」という意見もあるでしょう。さまざまな意見や感性があるのは当然です。
(法学館 憲法研究所 金井知明さん/弁護士 日本政府,国歌の強制で,国連機関から叱られる!?より)
■大人が守るのは子どもたち
最大の問題は、これが、日本が中国をはじめアジア諸国を侵略したとき、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。「学徒動員といって、学生さんたちを戦争に行かせて、結果的にみんな殺してしまったことになる。なぜなら神宮外苑で日の丸を振って、『君が代』を歌い、万歳と言って送り出してしまったから。もう、そういうことはさせない」という強い想いが過去の教員たちにはあったそうです。そういう教員の心情を無視した、排除のための「通達」だったのです。
さきの大戦で、侵略陣営の主力となったのは日本・ドイツ・イタリアの三国でしたが、この戦争中に侵略の旗印として使った旗を今もそのまま国旗としているという国はない。ドイツもイタリアも戦後、国旗を変えています。海外では君が代を聞くのも辛いという方もいらっしゃいます。それを強制的に歌わせるという「暴力」に私は賛同できません。「日本の反省は終わった」と言う方がいますが、このように残り続ける歌や旗があります。そして、強制してくる力があります。それは反省の姿勢ではなく、戦争に突入する考えです。だから私はたった1人であっても着席し、歌えなかった。歌わなかったのです。
国旗無し、国歌斉唱無しが一般的!?
旧文部省の初等中等教育局が1999年に作成した『国旗及び国歌に関する関係資料集』に基づくと、ヨーロッパ諸国において、国旗敬礼、国歌斉唱を学校で生徒、保護者、教員に強制している国は一つも存在しない。イギリス、フランス、ドイツ、 イタリア等では、そもそも入学式や卒業式等において国旗掲揚、国歌斉唱を行なっていない。
ヨーロッパ諸国でのこうした実情は、実は国際基準に沿うものでした。精神的自由の国際基準で今日、最も重要なのは、国際人権規約のなかの自由権規約であるが、その第18条は、
1項において、思想、良心、宗教の自由を定め、
2項 において、何人もそれらの自由を侵害するおそれのある強制を受けないと定めている。これらの規定に基づけば、例えば、ある人が一定の理由で国旗・国歌関係の儀式に参加しないという信念を自ら選択して有している場合、その自由を侵害するおそれのある強制を受けないということになる。
(思想・良心等に基づく拒否事件の類型別の 判断枠組(下) ―「国旗・国歌」強制事件の判断枠組の類型的特性―土屋英雄氏/筑波大学大学院人文社会科学研究科教授)
私たちは小学生の頃から当たり前のように歌わせられ、国を愛するような教育を受けていますが、愛するかどうかは、その人次第です。
その前に政府が国民に愛される政治をしていくべきです。この国が素晴らしいと実感できるような環境をつくっていくべき。本当に称えるべきこととは、この国で生きる人々が頑張って働いてきたこと、存在してきたことです。どんなに苦しい辛い状況でも歯を食いしばって頑張ってきた人たちがいた。無理な状況を耐え抜いてきた人たちがいた。その血と汗によってこの私たちの今があると考えます。
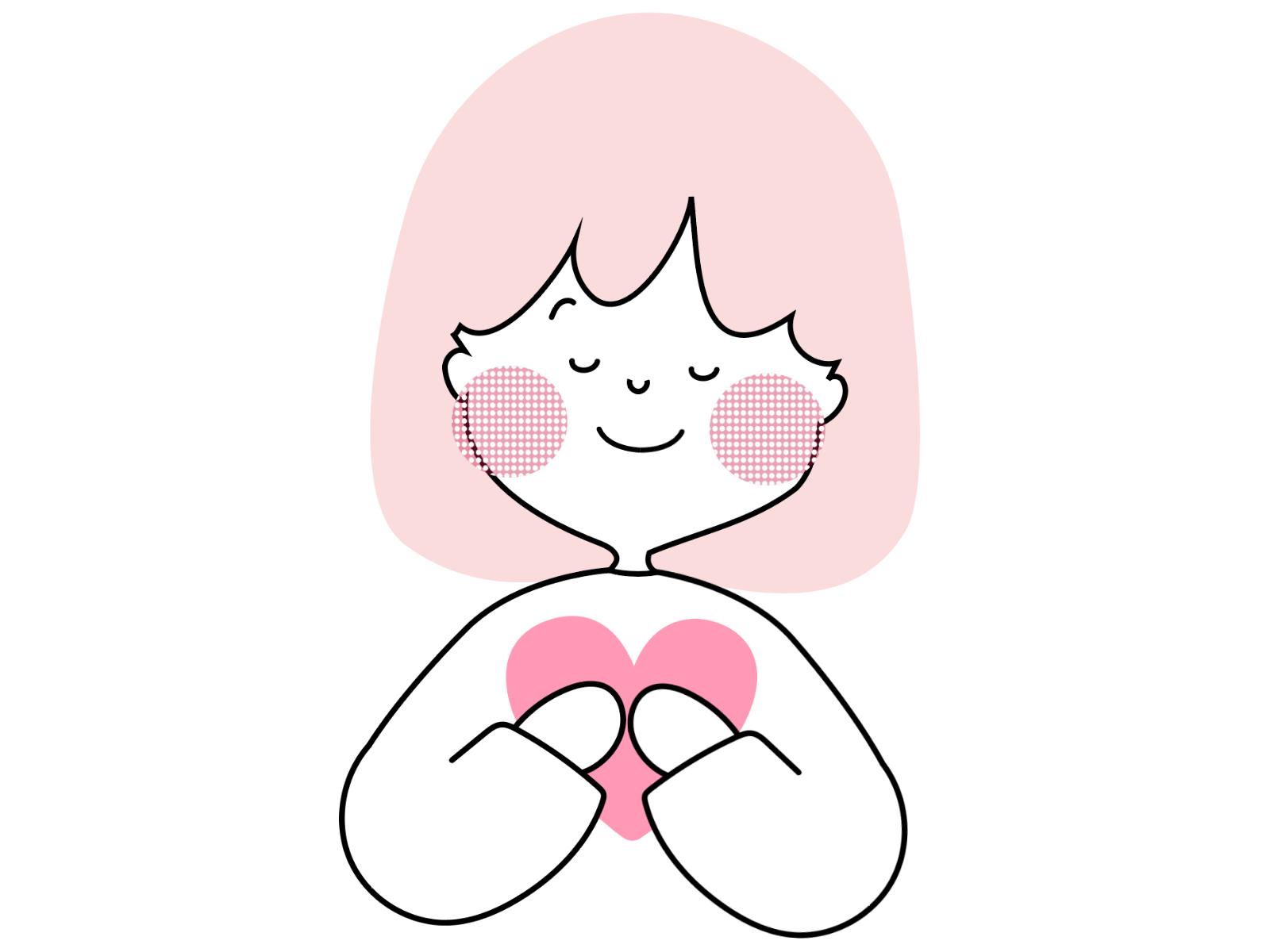 過去の人々からの目には見えないバトンが、今の私たちに手渡されています。多くの人々に感謝をすること、未来を壊さないことがお返しです。その感謝を急に「国」というものに繋げるのは、ちょっと横取りすぎだと考えますし、日の丸・君が代に繋げるような話でもない。
過去の人々からの目には見えないバトンが、今の私たちに手渡されています。多くの人々に感謝をすること、未来を壊さないことがお返しです。その感謝を急に「国」というものに繋げるのは、ちょっと横取りすぎだと考えますし、日の丸・君が代に繋げるような話でもない。
いつもみんなが頑張っていて、みんなで作り上げてる。だから一緒に変えたい。もっと住みやすい社会に。
■【動画で見る】石井れいこってどんな議員??
石井れいこYoutubeチャンネル 配信中!
この社会の問題は、1人じゃ戦えないです。
生活不安、息苦しさ、政治に無関心、それはあなただけのせいじゃない。
■【サポート募集】
是非私たちと一緒に活動をしましょう!
仲間はいつでも募集してます。
サポーター登録はこちら
■ご寄付はこちら↓
活動にはチラシ代、ポスティング代、活動費等どうしてもお金もかかります。れいわ新選組を拡げるお力貸してください。
ご寄付はこちらから
■【公式SNS】でも情報を発信してます。
是非ともフォローやいいね!よろしくお願いいたします。
2025年4月5日発行 / 石井れいこ & PEACE SCRUM