2024年2月の三鷹市議会(令和6年第1回定例会)石井れいこ一般質問「誰一人取り残さない命を守るインクルーシブ防災の徹底を」
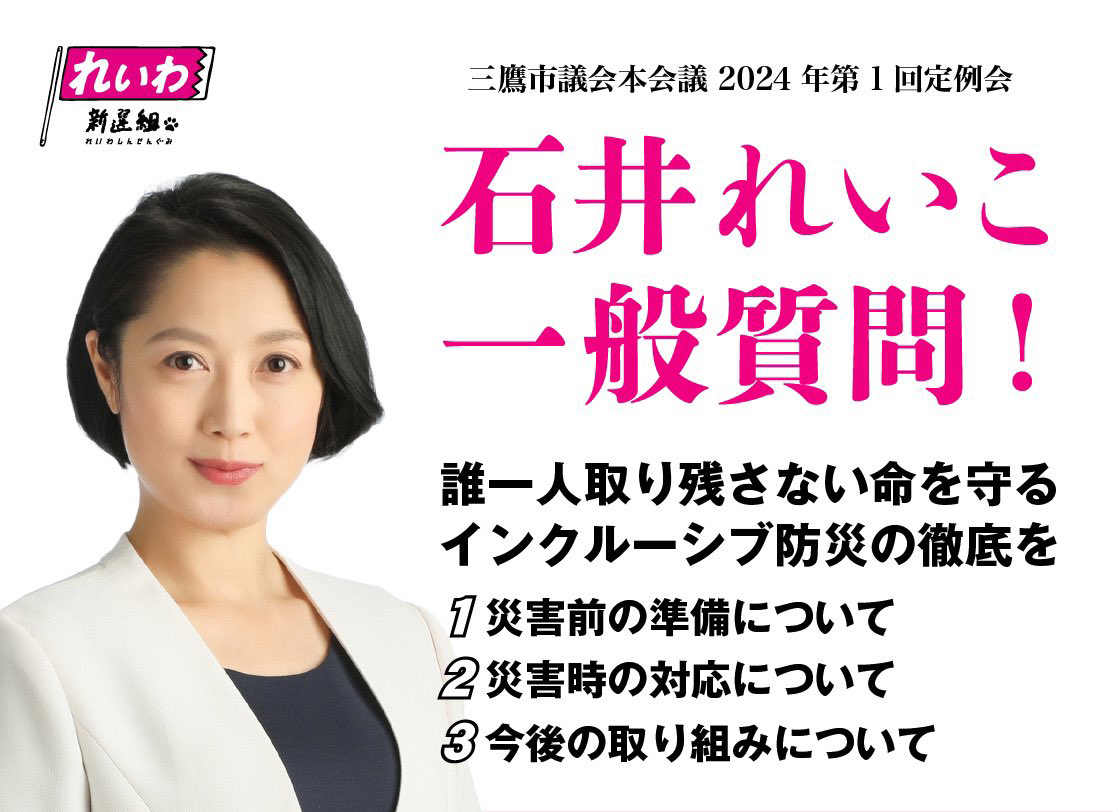
三鷹市議会(令和6年第1回定例会)
2024年2月26日 石井れいこ一般質問【動画】
テーマ:誰一人取り残さない命を守るインクルーシブ防災の徹底を
1.災害前の準備について
2.災害時の対応について
3.今後の取り組みについて
以下2024/2/26 令和6年第1回定例会(第1号)の私の一般質問の全文です。
2024-2-26:三鷹市議会令和6年第1回定例会(第1号) 本文
市政に関する一般質問
◯石井れいこ
よろしくお願いします。このたびの2024年1月の能登半島地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。また、現在も被災地で救援、救護、支援に御尽力されている方々、現地へ派遣された三鷹市職員へ感謝を申し上げます。一般質問を始めます。
1、誰一人取り残さない命を守るインクルーシブ防災の徹底を。
政府の地震調査委員会は、周期説に基づいて、2024年1月、南海トラフ周辺で今後マグニチュード8から9の巨大地震が発生する確率を、30年以内では70から80%程度と発表しました。しかし、阪神・淡路、東日本、熊本、能登など、多くの震災が、危険が低いとされている地域で起こっていることから、周期説にも疑いを持たなければならないと考えます。日本では、いつでも、どこでも、不意打ちで大地震が起こり得る、そう考えても間違いではないのかもしれません。
東日本大震災では、亡くなられた方の6割以上が60歳以上の高齢者、さらに、障がいのある方の死亡率は住民全体の2倍だったことが分かっています。その地域にいるはずの、障がいのある方が災害時にはいない、消えた障がい者という新聞記事があったように、合理的配慮がない恐怖で避難所に行けずにいる方や、うるさいなどの罵声を浴びせられ、やむなく車で寝る方など、頼りたくても頼れない状況が災害時には如実に現れます。
三鷹市においては、何年もかけて質の高い防災・減災のまちづくりを目指すと声高々に全市民に伝えてきたこともあり、市民からの期待は膨らみ、信頼は確立されつつあるのではないでしょうか。地域防災活動の目指すところは、この全市民の期待と信頼を裏切ることなく、災害が発生したときに、多様な住民の誰もが、一人残さず、ああ、助かった、避難所も清潔で安心だと言えるような地域をつくることを目指して行われる活動でなければならないと考え、質問いたします。
(1)、災害前の準備について。
質問1、2015年の国連防災世界会議では、私たち抜きに私たちのことを決めないでという言葉が繰り返し強調され、当事者参画が重視されています。障がい者をはじめとする様々な当事者を排除せず、誰一人取り残さない防災、復興を実現するために、国連が提唱しているインクルーシブ防災の理念に基づき、今後防災に関わる協議会や会議体には、高齢者、認知症の方やその御家族、女性、子育て中の御家族、障がいのある方やその御家族、LGBT、外国籍の方など、当事者を必ず参加させることを強く求めるが、三鷹市の現状と今後の予定を伺う。
質問2、石川県能登町の避難所において、女性の困り事や高齢者、障がい者への対応の難しさがあるとのこと。三鷹市の防災課の女性職員の人数と割合及び介護や介助に係る資格取得者配置の状況について伺う。
質問3、同様に、地域の方や学校関係者などで構成されている避難所運営連絡会のメンバーのうち、女性の人数と割合及び高齢者や障がい者に対応できる体制の状況について伺います。
質問4、災害弱者と呼ばれる方々を誰一人取り残さない対策のために、防災課において、震災を経験した自治体に直接現場の声や教訓等のヒアリングをし、全庁に共有すべきと考えるが、所見を伺います。
質問5、三鷹中央防災公園・元気創造プラザのパンフレットには、災害に強いまちづくりと多様な機能が融合した施設であると記載があるが、市民の災害時の利用に関しての具体的な記載がありません。広い周知がなされていない中で、災害時には何が利用できて、何が利用できないのかを事前に明確に示しておくべきと考えます。災害時の利用方法や機能を伺います。
質問6、災害時は混乱やパニックを起こしやすいと考えます。防災公園に大勢の人々が押し寄せることも想定すべきと考えます。アリーナ上部に当たる中央広場の重さ(荷重)制限について詳細を伺います。
(2)、災害時の対応について。
質問7、災害時の道路とは命をつなぐための生命線でもあるが、瓦礫、地割れ、水害のような形で車が利用できない可能性もあります。例えば、支援物資の運搬にはヘリコプターなど、車以外の輸送方法が想定されているのか、伺います。
質問8、石川県能登町の避難所では、更衣室や授乳スペース、子ども向けの遊び場がないところがほとんどで、粉ミルクや間仕切りもないところもあったそうです。避難所における女性の困り事、下着の干す場所、授乳スペースや子どもの遊び場の対応や対策について伺います。
質問9、高齢者や妊産婦、障がいの方に寄り添った福祉避難所がありますが、市内に何か所ずつあるか、伺います。
質問10、石川県輪島市では26施設と福祉避難所の協定を結んでいましたが、断水などの被害によって、被災後14日で開設できているのは7か所のみでした。ケアを受けたくても受けられず、壊れそうな自宅や車中泊を選ばれる方もいます。断水時に福祉避難所が利用できるよう、防災用の貯水槽、受水槽などの設置を市がサポートするべきと考えますが、所見を伺います。
質問11、震災特別非常参集態勢に基づき、三鷹市の震度が5強以上ですと、全職員が市役所に参集することになっておりますが、三鷹市在住の正規職員の人数と割合を伺います。
質問12、一刻を争う災害時の市民への対応を考えると、より多くの市職員に三鷹市に住めるように支援すべきであると考えます。そのために、家賃補助や職員住宅建設や借り上げ等が必要だと思いますが、所見を伺います。
質問13、福祉避難所等の民間施設の介護職員は必ずしも全員が三鷹市在住ではありません。道路や線路の故障によって職員が来られなければ、福祉避難所の開設もできません。よって、より多くの介護職員が市内に住めるよう、家賃等の補助をすべきと考えますが、所見を伺います。
質問14、復興までの道のりが長くなった場合、精神的にも混乱が生じ、性的な暴行をしてしまうという事例もあります。被災者が加害者になる前の心のケアに関して、対策を伺います。
質問15、断水があると、水洗トイレの利用ができません。災害時、避難所や公園等できれいで衛生的なトイレをいつでも利用できることを目指して伺います。国土交通省のガイドラインには、マンホールトイレの1基当たりの使用想定人数は50から100人を目安とすると記載されております。三鷹市の現在における洋式マンホールトイレや車椅子用マンホールトイレの保有数と使用可能想定人数を伺います。
質問16、そのうち、避難所となる施設の洋式マンホールトイレや車椅子用マンホールトイレの保有数と使用可能想定人数を伺います。
質問17、暑い夏の避難所における熱中症対策について伺います。
(3)、今後の取組について。
質問18、各地域で年に一度防災訓練がありますが、職種によっては休日の曜日や時間が違うこともあるため、地域の防災訓練には参加できない方々もいます。平日夜間の防災訓練なども検討すべきと考えますが、所見を伺います。
質問19、三鷹市が大災害に遭う場合、東京都全体が全体的に機能がストップすると考えます。姉妹市町の福島県矢吹町と兵庫県たつの市とは災害相互応援協定を結び、応援内容としては、大規模災害時の応急対策及び復旧対策とあります。二次災害からの避難という意味でも、災害弱者と呼ばれる方の希望があれば、双方の避難施設を利用し合えるような取組を盛り込むべきと考えますが、所見を伺います。
以上となります。よろしくお願いいたします。
●市長(河村 孝さん)
それでは、私のほうからまず御答弁させていただきます。
まず最初に、質問の1、市防災政策における要配慮者参画の現状と今後の予定についてということでございます。
防災に関わる市の会議体といたしましては、災害対策基本法に基づく三鷹市防災会議がございます。同会議は、三鷹市地域防災計画の施策及び推進等に関することを協議するため、年一、二回程度開催しております。会議の構成メンバーは多岐にわたりますが、委員40人のうち、要配慮者の方に関わる部門の機関からは、三鷹市社会福祉協議会、三鷹市障がい者福祉懇談会、三鷹市助産師会、三鷹市民生・児童委員協議会等から御参画いただき、様々な意見を頂戴しています。また、今後、分科会で幾つも分かれ、さらに関係の市民の方にも御参加いただき、実体のある様々な御意見をいただきたいというふうに考えております。そのほか、総合防災訓練、防災出前講座、避難所運営訓練など、様々な機会を通じまして、その企画段階から、こうした分野の方々と共に幅広く連携を図っていけるよう進めていきたいと考えております。
防災の問題は大変難しいというふうに思うのは、どの程度まで──どの水準まで例えば避難所を用意するか、そのための人の組織化を図るのか、あるいは備蓄をどのくらいまで求めるのかということを議論しようがないんですよね。いつ災害が起きるか分からないので。ある場合、備蓄品も期限切れになってしまったり、防災のために用意している様々な器具が使わずに──訓練などでは使うとしても、そのままになってしまうこともございます。ですから、防災の場合、どの程度のことが、どの程度の災害で、例えば避難所を、22か所でいいのか、100か所以上考えるのか、実際にやってみたら、自主的に公園などで避難されている方も多数いらっしゃる。今回の地震ではそのように聞いておりますから、100以上になるかもしれない、200になるかもしれない、そういうことになると、どうすべきなのかということを日頃から考えておく必要性と、ある意味、それが使わずに済んで、実際の場面で空振りしてしまうことは、これは別にそんなに──そんなにといいますか、批判されるべきことじゃなくて、よかったと思うしかない。例えば、台風のために避難場所をいろいろ準備しておいても、実際それる場合もあります。そうすると、台風が上陸してきたときに三鷹が大混乱になるかもしれないというふうに想定していたのに、その日は青空だったということはままあることなんです。そのときに、我々の構えとして、それは悪いことじゃないんだ、それ自体はあり得ることだということと、あと我々としては、地震だけが災害じゃない。この間ありました新型コロナの問題は、国では災害とは言っていませんでしたけれども、我々は災害のつもりで対応すべきだ、そういう非常事態であったというふうに理解していました。台風等の水害もそうです。あるいは、富士山が爆発するかもしれないというような話もあったり、様々な災害があることがあって、その全てに十全に対応することはなかなか難しいかもしれない。ただ、そのための準備を、100できないかもしれないけど、10でも20でも、やるだけのことはしたほうがいいということと空振りになるかもしれないということを我々は両方とも腹に置いて、この災害対策というのはやっていかなければいけないというふうに思っております。そういうことで、地域防災計画も、これもかなり歴史があるものでありますけれども、まだまだ具体的なところに入っていくにはこれからだというふうに思っていますので、これからもまた各担当のほうから答弁してもらいますけれども、不十分であることは確かであると思います。その十分さの水準がまだはっきり行政として、国も含めて、分かっているわけではない。ただ、準備を少しでも進めていくこと、今から対応することが──間に合う、間に合わないは別として、しっかりとしていく上での心構えだというふうに思っております。
私からは以上でございます。ありがとうございます。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
私のほうからは、市長の答弁を補足いたしまして、14点、順次お答えさせていただきます。
まず、御質問の2番目、防災課女性職員数、介護等資格取得者配置の状況についてでございます。防災課の常勤職員数は、現在派遣職員を含めて12名で、そのうち女性職員が3人、割合は25%となっています。また、介護や介助に関わる資格を所持する専門職としての職員配置はありませんけれども、防災対策については、防災課の職員だけではなく、平時の予防対策等の段階から福祉の分野の職員も関わる中で取り組んでいるところでございます。
続きまして、御質問3点目、避難所運営連絡会の女性の人数と割合及び高齢者や障がい者に対応できる体制の状況についてでございます。各避難所運営連絡会の委員構成につきましては、町会や自治会の会長、PTA担当者等が年度ごとに変更となることも多く、女性や介護の資格所持者の正確な人数及び割合について現状では把握できておりません。数年来のコロナ禍でこうした組織の活動も停止状態が続いておりましたけれども、昨年来、新型コロナウイルス感染症も法的な位置づけが変更になり、各地区の避難所運営連絡会も徐々に再開し、防災課職員も会議に参加する中で、実際に様々なお立場から多くの女性委員に加わっていただいている状況は把握しているところでございます。
続きまして、御質問4点目、被災自治体へのヒアリングと全庁での共有につきましてお答えいたします。このたびの令和6年能登半島地震では、石川県を中心に甚大な被害が発生いたしました。被災地では多くの方々が避難生活を余儀なくされており、避難生活の長期化も見込まれる中、災害弱者の方をはじめ、多くの被災者への生活支援や被災地の復興に対応するための人的支援が必要となっています。そうした中で、東京都では発災直後から能登半島地震支援対策調整会議が立ち上がりまして、現地の被害状況について庁内での情報共有を図るとともに、被災地支援に向けた職員派遣等を行っております。三鷹市におきましても、現在、東京都を通じ、輪島市に順次2名の職員の派遣を行っております。今後、派遣職員から現地の状況等を報告してもらうほか、これまでも阪神・淡路大震災で支援を行った芦屋市、新潟県中越地震で支援を行った栃尾市──現在の長岡市です、東日本大震災で支援を行った矢吹町などから、職員を派遣するだけではなく、後日様々な教訓を学ぶ取組を行っており、その内容について、その都度、市の災害対策等にフィードバックすることとしております。
続きまして、質問の5点目になります。三鷹中央防災公園・元気創造プラザの災害時における利用方法や機能についてでございます。三鷹中央防災公園・元気創造プラザは、総合防災センター機能を持つ、災害対策活動の中核を担う施設として、震災時には通常の施設利用から各階、各機能を転換して、建物全体が市災害対策本部をはじめとする災害対策の活動拠点となります。このため、施設内の各室入り口の表示板には、通常時の各階、各室名と併せまして、災害時に転換する機能についても各室ごとに表示されており、平時から施設利用の方々への周知も行っております。一方で、三鷹中央防災公園・元気創造プラザは、外の防災公園部分を中心といたしまして、一時避難場所にも指定されておりますので、議員の御指摘のとおり、施設全体が避難所、避難施設となるものと混同される可能性もあると思われます。引き続き、三鷹市防災マップや防災出前講座など、様々な機会や媒体を通じまして、市民の誤解が生じないよう、さらなる周知に努めてまいりたいと思います。
続きまして、御質問の7点目になります。支援物資運搬時における車両以外の運送方法についてです。令和6年能登半島地震では、各地で道路が途絶したことから、災害応急対策を実施する関係機関の情報収集及び人員の輸送、救助、救出活動、孤立集落への物資輸送などに当たって、機動力のあるヘリコプターが効果的に活用されているものと承知しています。今回のこうした状況を受け、地域防災計画における航空機等の輸送に関する記載の見直しについて国からも通知があるなど、市の地域防災計画におきましても見直しを行い、発災時の緊急輸送手段としてヘリコプター等の活用が有効と考えられる場合には、ヘリコプターの派遣要請も含め、より柔軟に対応が可能となるよう取り組んでまいります。
続きまして、御質問の8点目になります。避難所における女性や子どもへの対応や対策についてお答えいたします。三鷹市では、避難所ごとに設置しております避難所運営連絡会において避難所運営マニュアルを作成し、その中で女性専用の着替え場所、洗濯場、洗濯物干し場、授乳スペースを確保するなど、女性が安心して避難生活が送れるよう取組を進めております。引き続き、避難所運営への女性の参画を推進するとともに、女性の視点からの対策をさらに進めるべく、関連団体や組織等とも連携しながら、要配慮者対策の一環としてその取組を進めてまいります。また、子どもの遊び場や居場所づくりにつきましても、今後の課題といたしまして、先進市の設置状況等、同様の取組として調査、検討してまいりたいと思います。
続きまして、御質問9点目になります。福祉避難所の設置数についてでございます。三鷹市内の福祉避難所は現在29か所となっております。その内訳は、障がい者施設が15か所、高齢者施設が12か所、就学児施設が2か所で、妊産婦用は現時点でございません。引き続き、民間施設を中心に、その拡充に取り組んでまいりたいと思っております。
続きまして、御質問10点目、福祉避難所施設における貯水槽、受水槽設備への支援についてです。飲料水用の給水拠点は、市内上連雀給水所及び三鷹新川給水所に加え、第三中学校など、6か所の公共施設に貯水槽を設置し、合計9,430立米の飲料水を確保する体制を整備しておりますほか、市内の避難所全33か所には、耐震化された水道管から直接給水できます応急給水栓を設置し、多様な手段による飲料水の確保に努めているところでございます。また、生活用水の給水拠点は、第一小学校など、13か所の公共施設に整備しているほか、市民が所有する井戸を災害時に活用できる震災用民間井戸を市内39か所指定しております。現時点におきまして、福祉避難所に対する貯水槽や受水槽設置に対する支援を実施する予定はございませんけれども、今後も、貯水槽等の設置にかかわらず、福祉避難所開設に伴う多様なニーズの把握には努めてまいりたいと思います。
続きまして、御質問の14点目になります。被災者に対する心のケアにつきましてお答えいたします。大災害時には、特に弱い立場に置かれ支援を必要とする女性や子どもが被害に遭う暴力や性被害が発生し、また被災者やボランティアなどの支援者のどちらもが、被害者にも加害者にもなり得ると言われております。三鷹市地域防災計画では、避難所における要配慮者への取組といたしまして、避難所の避難者の不安、疑問等に関する相談窓口を設けることのほか、被災者の心身の健康維持を図るため、市の医療健康班を中心に、保健師等の保健活動チームを編成し、各避難所等への巡回健康相談の実施や東京都の精神相談チーム等の巡回によるメンタルヘルスケアを実施することなどを想定し、対応することとしております。
続きまして、御質問の15点目、市内のマンホールトイレの状況と使用可能想定人数について、同じく16点目、避難所となる施設におけるマンホールトイレの状況について、関連がございますので一括してお答えいたします。
三鷹市における災害時のトイレ対策の現状といたしましては、避難所を中心に、組立て式トイレ331台や排せつ物を密封して細菌も遮断するラップ式ポータブルトイレ67台を配備しております。また、マンホールトイレにつきましては、市内3つの公共施設に合計で29基、うち車椅子対応可能なものが5基整備されております。
このうち、避難所となる施設におけるマンホールトイレとしては2か所で計9基の配備があり、うち洋式が3基、車椅子対応可能なものが2基となっております。なお、マンホールトイレの1日当たりの使用可能想定人数につきましては、マンホールトイレの整備・運用のためのガイドラインに基づき、1基当たり100人程度を想定しているところでございます。
続きまして、17点目、避難所における熱中症対策についてです。避難所におきましては、多くの避難者が体育館で避難することを想定しております。このことから、熱中症対策といたしまして、学校体育館やコミュニティ・センター体育館における空調設備の整備を推進しております。また、分散型エネルギー確保の観点から、電気式、都市ガス式、LPガス方式のエアコンをそれぞれ取り入れて対応しているところでございます。
続きまして、御質問の18点目、防災訓練等の平日夜間実施につきましてお答えいたします。市では、年に一度の総合防災訓練を各地域の自主防災組織が計画して実施しており、できる限り多くの方に参加をいただけますよう、通常は土曜日または日曜日の昼間に実施しております。また、そのほかにも、年間を通じまして、これまでも地域や参加者の実情に応じたミニ防災訓練や防災の意識啓発活動など、平日や夜間にも実施しているものもございます。市民の皆様の生活スタイルも様々でありますので、これからもできる限り多くの市民の皆様が参加しやすい曜日や時間帯での防災への取組を進めていきたいというふうに考えております。
私からは最後になります、19点目、姉妹市町との相互の避難施設への二次避難についてお答えいたします。福島県矢吹町と兵庫県たつの市とは、それぞれ災害相互応援協定を締結しております。議員御指摘のとおり、両市町とは、この協定に基づきまして、大規模災害時の応援対策及び復旧対策が相互に実施される内容となっております。これら協定では、さらに応援要請の内容といたしまして、大規模災害が発生し、応援を求めようとするときには、連絡担当部局を通じて、役務の提供、救援物資の調達その他必要な措置を要請するものといたしまして、要請を受けた側は、極力これに応じ、救援に努めることとされております。御質問の災害弱者の方の二次災害からの避難に伴う避難施設の提供につきましては、現行の協定では事態を想定した対象施設等に関する取決めはありませんけれども、具体的なニーズが生じた場合には、その条件や内容について協議、検討を踏まえた合意を前提に、現協定のままでも相互に十分対応可能なものというふうに認識しております。
私からは以上になります。
●スポーツと文化部長(大朝摂子さん)
私からは、御質問の6点目に答弁をさせていただきます。
中央広場の重さ制限について、中央広場を設計した際の考え方といたしまして、まず有効避難面積は1人当たり2平米を確保するものというふうな考え方で設計をしております。なので、避難人数としては、中央広場の敷地面積は約3,300平方メートルであることから、1,650人を想定しております。一方、中央広場の重さ制限ですけれども、1平米当たり240キロというふうに考えております。1人当たりの体重を平均で65キロとした場合、1平米当たり3.7人、2平米にそろえますと7.4人というふうになりますので、中央広場の安全性は十分確保されているものと考えております。
●総務部長(高松真也さん)
私からは、災害時の対応に係る御質問のうち、11点目、市内在住の正規職員の人数と割合及び12点目、家賃補助や職員住宅の必要性について、一括してお答えをいたします。
令和6年1月1日現在、市内在住者は、常勤職員1,045人のうち235人、全体の22.5%となっており、近年は22%前後で推移をしているところでございます。なお、近隣市区の武蔵野市、府中市、調布市、小金井市、世田谷区、杉並区に居住する職員が394人おりまして、市内在住者と合わせますと629人、全体の60.2%となりまして、緊急時の参集態勢につきましては一定程度確保できているものと認識をしているところでございます。
したがいまして、他の自治体において、職員用の住宅を用意したり、区域内に住む職員に対し家賃補助相当の住居手当の上乗せをしたりしている事例があるということは承知をしておりますけれども、現時点で新たに家賃補助、家賃の助成等を実施することや職員住宅を借り上げることなどは考えておりません。
居住地の選択に当たりましては、職員個々の考え方、また経済的事情等を踏まえまして、職員自らが判断することを尊重すべきであると考えております。その一方で、職員が市内に居住することは、職員自身の生活復興や家族への支援を踏まえつつ、災害発生時に市民への継続的な支援を可能とするために重要な課題の1つであると認識しておりますので、今後、他自治体の事例等を含めて調査研究を進めていきたいと考えております。
以上です。
●健康福祉部長・新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局長(小嶋義晃さん)
私からは、市長の答弁に補足いたしまして、質問の13点目、福祉避難所開設のための介護職員への家賃補助について答弁させていただきます。
福祉避難所を開設する際に重要な役割を担う介護職員の確保、定着支援につきましては、市といたしましても喫緊の課題として捉え、資格取得補助や永年勤続表彰といった取組を行っているところでございます。なお、現在、東京都において介護職員宿舎借り上げ支援事業といった同様の趣旨の事業を実施していることなどから、市として新たに介護職員に対して新たな家賃補助制度を設ける予定はございませんけれども、災害時には福祉避難所の開設、運営が少しでもスムーズに行えるよう、福祉避難所協定締結法人との連携に努めてまいります。
以上でございます。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
質問1から行きますね。どの自治体もちゃんと防災はされていると思いますし、精いっぱいだと思います。でも、しかし大震災となればどうにもならないということもあるので、誰一人取り残さないというために我々は何ができるのかというのをやはり常に考えていかなければいけないのかなと思います。質問1も、当事者を含めてほしいということなんですけど、当事者といっても、実際に日々困られていることがある、災害時にはもっと困ることがあるという方々からもお話を伺うという体制をつくっていただきたいのですが、その点いかがでしょうか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
再質問にお答えいたします。
日々お困りの方への対応ということなんですけれども、先ほど市長が答弁申し上げたとおり、一応、日常的には防災会議という中で計画等も含めて審議をお願いしているところですけれども、実際の例えば福祉避難所をお願いするとか、そういった個別の事案ごとにやはり配慮の内容も様々あると思うので、そういった、例えば避難所をお願いする際にはどういった分野の方なのかということを個別にやはり丁寧に対応していくことが必要だと思いますので、そういった避難所開設の御相談であったり、またそういう個別の施設のほうで何か訓練を行いたいというお話であれば、それに対してこちらでも対応したりとか、そういったやはり地道な取組になるのかと思いますけれども、そういったことで底辺を広げていくということが非常に重要なことだというふうに認識しております。
以上です。
◯石井れいこ
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
続いて、質問2の件ですが、東日本大震災女性支援ネットワーク調査チームに寄せられた性暴力の事例なんですけど、82件、うち11件は10歳未満の子どもが被害者だったということで、20代から60代まで、年齢層が幅広いということも分かっています。日頃から強くない立場の人が、被災ということで、災害に遭うことで余計に脆弱性が増してくるわけで、赤ちゃんに授乳しているところをすごく見られているとか、下着や生理用品については女性に相談したいなど、実際に災害時に女性の運営メンバーもいてくださると助かるという声がすごくあります。男性にはやはり話しづらいという女性の方もいらっしゃるので、そういった意味で、対応できる手厚い体制を整えるよう促してほしいんですが、いかがでしょうか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
お答えいたします。
避難所運営ということになると思うんですけれども、三鷹市の場合、各避難所を、地域の避難所運営連絡会ということで地域の皆さんに立ち上げていただくというのを、当初3日間を想定して位置づけております。ですので、そういった地域の皆さんに担っていただく中で、当然、そこに女性の方に多く加わっていただくことで、今、議員御指摘の部分が解消していくものとなります。先ほど御答弁申し上げたとおり、そういった避難所運営の中に常時入れるかどうかはあれですけれども、市のほうでそういった専門職のほうが回って、そういったニーズが漏れないような対応も必要だと思いますけれども、まずはそこの地域の避難所運営を担う方々に、女性に多く参加いただいて、そういった課題にも認識いただくということでの対応が第一義になるのかなというふうに認識しております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
あと、同様に避難所の運営のところなんですけど、障がいのある方や災害弱者と呼ばれる方々は、実際に避難所に行ってみたけど、避難所運営の方々の理解が得られなくて、絶望的な場所になってしまったということで、崩れそうな家に戻ったりとか、車で無理やり寝泊まりしなければならないという状況があるそうです。熊本県が作成した障がい者の特性に応じた平時・災害時の対応指針がとても、すごくありがたいなと思ったんですよ。障がいの特性があって、その障がいのある方が避難行動時に必要とされる支援、そしてその障がいのある方が避難所などで配慮すべき事項というふうに細かく掲載されていて、それは誰が見ても分かるのかなと。その人たちだけじゃなくても、みんなで手伝った場合には、この人はこういうタイプだよというのが分かって、これは災害時じゃなくても、常に把握しておくことでもいいのかなと思ったんですね。なので、そうやって誰でも分かるようなマニュアル、指針をつくっていただけたらありがたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、避難所のほう、なかなかそういった専門的な知識をお持ちの方がいない中で、今言われたようなマニュアルだけでどこまで対応できるかなというのも正直あると思います。従前は三鷹市の場合も福祉避難所というのを二次避難所に位置づけをしていて、まず一般の避難所のほうにそういった方々もいらっしゃる想定をしていたんですけれども、前回の地域防災計画の改定で、福祉避難所をしっかり一次避難所として位置づけられるように、施設の協定を締結して増やしています。一義的には、従前から関わりのある施設のほうにそういった方々も避難できるような体制を完璧に、100%はなかなか難しいと思うんですけれども、そういった入り口をしっかりつくるような形での取組を進めつつ、今、議員がおっしゃるような、一般の避難所の中でも共通認識を得られるような、そういった情報共有の仕組みは大切だと思いますので、その辺りもちょっと今後研究してみたいと思います。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
ぜひとも、災害にかかわらず、常に皆さん、そうやって障がいのある方特性を把握しておくのはいいことかなと思うので、ぜひともお願いしたいです。
あと、福祉避難所なんですけど、必ず、この障がいの方、この高齢者の方はこの施設に行くというのが全て確定されているのか、それともされていないのか。恐らく、されていないと不安が大きくなってくるのかなと思うんですけど、その点、いかがでしょうか。
●市長(河村 孝さん)
避難所の件をずっと詰めていくと、今、御質問者が言われているように、どんどん細分化されてくるんです。誰一人残さないとかね、個々人の、障がいを持っているとすれば、その度合いも違いますし、いろんな分野も違うとかということで、日頃から通い慣れている福祉施設で、例えばデイサービスに行っていたとすれば、そういう方はそういう場所のほうがいいんではないか。例えば、そこで福祉の職員の人はその人の個別性をよく知っているので、薬のことも含めて、かなり面倒が見られるんじゃないかというふうなことが例えば想定できます。実際に東日本のときも、各施設の──例えば、福祉のヘルパーさんが自分の担当している高齢者のところに個別に回った。特に指示がなくても、そういう形でフォローしていたというふうなお話も聞いています。ですから、東日本以降、そういう傾向になりつつあって、三鷹市でもそのように、それぞれ持っている個別性が──地域が主体であったときに、避難所が学校に限定されていたのに加えまして、さらにいろんな個別性、福祉の分野だとか、あるいは外国人だとか、あるいはペットを持っていらっしゃるとかいう形になってくると、それぞれに向いたところをいろいろお聞きしながら用意していく必要があるのではないかということで、今、取り組み始めた端緒といいますかね、そういう段階です。ですから、福祉のほうでも、おひとり暮らしの方で現在ヘルパーさんが行っているところについては、もしも何か災害があったときに、パートナーという形で、その方を特定の避難所まで連れていくような、そういう仕組みも今検討し、その渦中にあるところでございます。そういう意味で、それぞれのところが今まさにつくられつつあるというふうに御理解いただいたほうがいいのではないかと思います。不十分な部分はまだまだ、これからたくさんあると思いますが、そういう解決に向けていっています。
ただ、もう一つ重要なのは、そういうふうに細分化されたり、地域でも御近所にそういう公園なんかで避難されている方や何か、全体をどのように把握するのかというもう一つの──細分化した後に、トータルに避難者を把握しておくことがないと、例えば水にしても食料にしても届けられないということがありますから、そういう全体の把握をどういうふうにしていくかという問題もさらにその次には待っているというふうに思っています。
ですから、そういう意味では、災害対策というのは今、第1歩、第2歩、だんだんとよくなっていますけれども、まだ初歩的な段階だというふうに思っていますので、これからもっともっとしっかり構築していくのかなということが、私ども三鷹市だけではなくて、東京全体でもそうですし、そういうことが課題になりつつあるというふうなことだというふうに理解しています。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
そうですね。これからと言われてしまうとあれなんですけど、ふだん通っているところに行かれるというふうに、そういう想定になっているということなんですけど、いつもは車で移動していたけど、車が通れないとか、その車が本当に来るのかというのは、やっぱりその人たちが不安になる要素ではあるので、そういうのも含めて今後計画に入れていってもらえたらありがたいです。やっぱり、福祉避難所が一次避難所になるというふうに言っていたんですけど、そこが断水してしまったらば、トイレも使えなかったりとかしてしまうというのがあるので、それもやっぱり、その場合、その施設に貯水槽なり受水槽なりがないと、水をどうするのかというのも不安で、結局、能登、輪島市じゃないですけど、あるけど開けなかったということになるかと思うんですよね。その点、やっぱり介護職員の人たちもそうで、三鷹市に住んでいる人だけじゃないと思うんですよ。なので、その点もやはり都でやっているからというだけじゃなくてね、もうちょっと手厚く、三鷹市のためにお願いしますという形で補助すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
福祉避難所についてですが、そうですね、御指摘のとおり、断水の場合、多分、市内全域がかかった場合、当然、福祉避難所だけでなく、全世帯であったり、避難施設もそういう状況になるということで、なかなかマンホールトイレは、先ほども御答弁ありましたけれども、設置するにはかなりの費用もかかるという中でありますので、取りあえず組立て式の簡易型のトイレであったり、そういったものをやはり水が通るまでの間はちょっと頑張って使うしかないのかなという部分もあって、そういったものの備蓄にも努めているところです。また、福祉避難所のほう、協定を締結して、幾つか、今どんどん増やす取組を進めているんですが、そういった災害用の備蓄のトイレであったり資機材についても受け入れていただければお預けして、必要なものということはあるんですけれども、なかなか施設側のほうで、スペースの問題であったり、またそういったものを管理する体制であったりという課題もありまして、すぐにそういったものも常時現場のほうに置けないような現状も今ございます。また、議員御指摘のとおり、施設までの移動の手段ということも大きな課題だと思っています。これは要配慮者の方だけでなく、市内、災害時、移動手段の確保というのは非常に、災害医療なんかも含めて課題の多いところでございますので、そういったいろんな課題に一つ一つ、やはり対応していかざるを得ない状況でありますけれども、そういった中で、福祉避難所につきましても同じような取組の中で、少しずつですが、進めていきたいというふうに思っております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
続いて、マンホールトイレの話が出たんですけど、登山家の野口 健さんという方が海外の支援者から、日本の避難所はソマリアの難民キャンプ以下だと、国際的なスフィア基準を満たしていないと聞いたそうで、驚いたそうです。多くの人が当たり前だと思っている日本の苦痛を強いる避難所なんですけど、災害時でも人間らしい生活を送れるようにするスフィア基準の理論は、避難所の1人当たりの専有面積、男女のトイレ比など、内閣府が言っているように、決してぜいたくなどではなく、災害時だからこそより人々の尊厳を守るという大切な国際基準であります。公助としても指針にすべき基準と考えます。ですので、今の数、大震災になった場合に到底足りないと思うんですよね。断水になった場合、マンションの人たちがみんなトイレを使えないとなったらばどうするのかということもあると思うんですけど、どう増やしていくのかの計画とかを聞いてもいいですか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
お答えいたします。
災害時のそういった対応の中で、施設の数なんですけれども、やはり考え方はいろいろあると思いますけれども、一定の想定数については、人数的に今、市内の施設で収容できる前提で準備はしております。また、ここ数年のコロナ禍の関係で、感染症対策ということで、ちょっと先ほどの御指摘とは違う意味なんですけれども、やはり一定のスペースを各自、各世帯ごとに取らなければいけないということで、パーティションであったり、そういった配備を増やしたり、あと従来ですと体育館のみを学校の中の避難所として想定していたんですが、やはり教室のほうも使わせていただかないと収まらないんじゃないかというようなことも検討しております。また、先ほどマンションの話も出ましたけれども、被害の状況によっては、断水とかでライフラインが一部途絶える場合はあると思うんですが、建物自体それほど影響がない、躯体に影響がない場合、ぜひ在宅での避難ということもやはり一方で進めなければいけないと思っております。そういった在宅避難の方について、今度は一定のそういった炊き出しであったりトイレの問題であったりは、お近くのほうに在宅生活者の避難支援施設というのを今、同時に整備を進めておりますので、そういったところで一時的には避難していただいて、自宅のほうで寝泊まりはしていただけるような、そういった取組も避難所の充実と併せて進めていきたいというふうに今現在取組を進めております。
◯石井れいこ
分かりました。
では、実際に災害用のトイレを利用する訓練などはあるんでしょうか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
トイレの訓練の御質問でございますけれども、総合防災訓練ではよく地元の中学生の方に事前に学習していただいて、特に上物中心なんですが、組み立てる部分までの訓練は常時、市の防災訓練でも行っておりますけども、実際にそのトイレを使ってみるというところまでは今現在まだ訓練では行えていないのが実際でございます。その辺のやり方につきましても、これは各地域の皆様と訓練のほう、計画、企画段階から行っておりますので、そういったことも今後検討する必要があるのかなという中で、一緒に対応をできたら考えていきたいと思っております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
地域によっては、まち全体の大きなお祭り、みんなが集まるようなお祭りを防災活動として、防災とは言わない、いつものお祭りに防災をくっつけるという考え方を持ち込む地域もあるそうです。そういうところに実際にトイレを設置してみたりとかして、実際に利用してみたときに課題とかも見えてくるのかなと思うんですけど、そういう地域のお祭りと防災をくっつけていくという取組とかはいかがですかね。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
各地域での様々な催し、そういったところで今御提案のようなものを使うというのは非常に、他の自治体でも最近いろいろ行われているというのは承知しております。なかなかちょっと今、私ども防災課の部署で、そういった市内各所で行っている様々な取組をちょっと把握できずに、そういうお声がけもできない状況でありますけれども、このたびNPO組織も立ち上がりましたので、そういった団体とも連携して、地域の情報を拾う中で、そういった取組もできないか、そういったNPOとも協議しながら進められたらというふうに考えております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
あと、質問19の姉妹市町の話ですが、アメリカの歌手のテイラー・スウィフトさんがアジアのツアーを回っていて、日本に来たときに、自分の鼻がおかしくなったと思ったそうなんですね。日本の匂いだけが異常だと。それは、まちが全然臭くなかったということなんですね。このように、今の現代は、虫も飛ばない、きれいな水洗トイレなどが利用できて、とてもきれいな環境で私たちは暮らしているんですけど、やはり大震災の様子をテレビで見ると、もう耐えられないと──子どもを守り切れるのかとか、育てられるのかとか、不安があります。私らはもういいからという高齢者の声とか、障がい者に関しても生きることを諦めてほしくないと思いまして、事前に避難できる姉妹都市の現地を見ておこうという、そういう企画とかをつくったりとか、旅行につなげるということもいいのかなと思いまして。ただ、障がいのある方の中には、不慣れな環境は落ち着けないという人もいるので、事前に画像とか動画を撮っておくということもできたらいいなと思います。言葉で言うほど簡単ではないんですけど、そういう姉妹市町と避難所という、可能だとはおっしゃっていたんですけど、そういう意味でも、旅行につなげるなど、仲よくできたらと思うんですけど、いかがですかね。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
姉妹市町とのやり取りですけれども、先ほど御答弁申し上げたとおり、今の協定でもそこは十分に対応可能かなということで認識しております。ただ、前回、東日本大震災のときに矢吹町も一定の被害がありまして、三鷹のほうからも支援を行ったんですけれども、その際、逆に矢吹のほうから、こちらに避難したいというようなお話というのは実際なかったんです。距離が結構、やはりどうしても200キロぐらい矢吹町はありまして、たつの市ですと600キロぐらい離れているということで、そういった離れた距離に避難するというのもなかなかちょっと、避難される方の意識的にもどうなのかなということでございますので、もしそういうニーズがあれば当然協議は可能だと思うんですけれども、今現在は先ほど御説明したとおりの内容で対応可能ですが、今現在は、物資であったり、人の支援を相互に行うというのが前提の協定というふうに理解しております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
続いて、防災公園のほうに行きます。まちの声として、話したら話した分だけなんですけど、全員が、災害時は防災公園に行けば何とかなるというふうに思われている方が多くて、防災公園を家族との待ち合わせ場所にしておこうと思われている方がいらっしゃいます。それは地域の防災訓練に参加されていない人だったりするんですけど、防災訓練に参加されている人というのは結構僅かかなと思うので、多くの方が防災公園というのをすごく巨大な何かができるものだというふうな幻想というか、あるのかなと思いまして、中央広場に荷重がかかるとアリーナが落ちてしまうということもやっぱり知らないという方が多かったです。やっぱりパニック状態になると人が大勢集まることも想定すべきことかなと思いまして、何か重たいものを持ってきてしまうかもしれないという方もいるかもしれないと思います。
あの場所に、中央広場に仮設テントは建つ予定があるんですか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
中央防災公園のほうなんですけれども、特に仮設テントというのは今想定はなく、一部、防災パーゴラという、テントのようなものなんですけども、そういったものは1か所、東広場のほうにございます。取りあえず、先ほども御答弁申し上げましたけれども、元気創造プラザの建物、またスポーツセンターの内部については、先ほど申し上げたような災害対策の実施本部、またその他関連施設ということで、避難所とはならないんですけれども、外の防災公園については一時避難施設ということで、あれだけ広いスペースありますので、そちらのほうに当然、先ほど議員御指摘のような状況のときには人が皆さん集まってこられるということは一定の想定はしているところです。そちらにお集まりの方について、またその後の避難所であったり、そういった施設については適宜適切に御案内もできると思いますので、集まった方に何も対応できずということよりは、防災対応の起点にはなっておりますので、そういったいらした方への対応、御案内にもしっかり取り組む予定で対応していきたいというふうに思っております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
先ほど重さのことを言っていました。1平方メートル当たり240キログラム。何年前かな、以前のやつだと300キロとなっていたんですけど、240キロになったんだなというふうに考えまして、大きな人がどーんと尻餅つくと、その人の体重以上のものがかかると思うんですけど、そういうのも大丈夫なんですかね。
●スポーツと文化部長(大朝摂子さん)
1平米240キロなので、1平米って畳半畳分ぐらいですね。そこに平均60キロから70キロぐらいの方であれば3人から4人。240キロというと、かなり巨体なお相撲さんがお一人分ですよね。なので、基本的には計算上、例えば日常的な使用で、災害時じゃなくても、今のところ幸いそういう事例はないですけれども、例えば中央広場で具合が悪くなった方が出たときに救急車が上に上がるということは想定をしております。救急車、おおむね4トンぐらいあるというふうに言われています。そこから割り返して、1平米240キロ、240から300、少し幅があると思います。なので、基本的に人が──大きな重機が小さい点でぎゅっと何か荷重をかけるとかいうようなものであれば、面で受けるとかの配慮が必要なんですけれども、人が普通の状態で上に乗っていただく際には、お相撲さんが乗っても大丈夫というようなキロ数になっていますので、そこで転ぶとか跳ねるとかということもあっても、基本的に大丈夫という前提で計算はなっております。
◯石井れいこ
ありがとうございます。
建物なんで、経年劣化というものもあったりするのかなと思うんですけど、メンテナンスはどのくらいに一度されているんでしょうか。
●スポーツと文化部長(大朝摂子さん)
メインアリーナ自体のはりですとか、そういうものについてのメンテナンスというのは、今のところできて7年目ですので、まだ行っておりません。定期的な10年点検ですとか、15年点検ですとか、この後、確かに経年劣化というのはあり得ますので、定期的な点検はこの後発生してくるものと思われます。
◯石井れいこ
分かりました。
あと、防災公園全体についてなんですけど、かまどベンチというのがあります。かまどベンチを利用して炊き出しをしたとか、訓練として使ったことって何回ぐらいありますか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
防災公園のかまどベンチですけれども、あちらが完成した当初、お披露目という形で使用したことはあると思うんですけれども、近年あちらのほうで行っている訓練というのは、水防訓練とか、そういったところで会場を使っておりますので、ここ最近はちょっと実際には使えていないという状況でございます。
◯石井れいこ
多くの市民が防災公園で何かができるというふうに思っているんですが、実際は、じゃあ、一時避難のみ、もしくはトイレ、マンホールトイレが使えるという認識で大丈夫でしょうか。
●総務部危機管理担当部長(齋藤浩司さん)
御答弁、お答えいたします。
基本的に、かまどベンチであったり、マンホールトイレの設備がございますので、起こった災害の程度だったり、お集まりの方の避難者数に応じて、しっかりそういった機能を使用できるように対応する予定でございます。
◯石井れいこ
市民の方々に誤解のないように周知、引き続きよろしくお願いします。
以上、終わります。
■【れいわ三鷹サポーター募集】
是非私たちと一緒に活動をしましょう!
仲間はいつでも募集してます。
サポーター登録はこちら
■ご寄付はこちら↓
活動にはチラシ代、ポスティング代、活動費等どうしてもお金もかかります。れいわ新選組を拡げるお力貸してください。
ご寄付はこちらから
■【公式SNS】でも情報を発信してます。
是非ともフォローやいいね!よろしくお願いいたします。